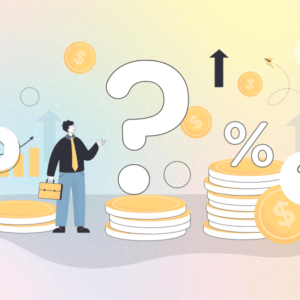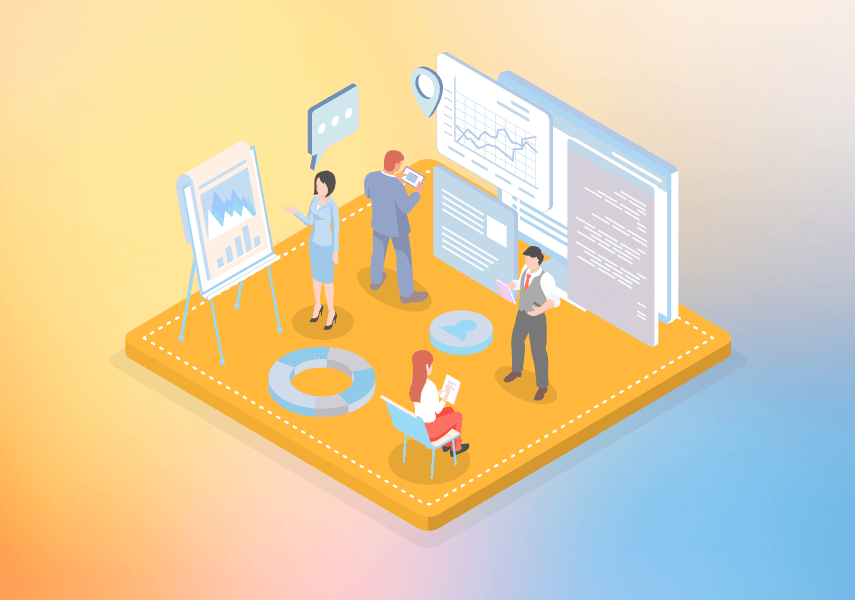
【第20話】「配当」からわかること まとめ④ ススム先生の「タイパ決算書分析」塾
「タイパ決算書分析」塾、第20回。今回はタイパな分析のまとめ、4回目です。今回はマナミさんが大好きな配当について整理しましょう。
はい! 頑張ります。
先生、それより「トランプ関税ショック」ですよ。この先どうなりますか?
ここ数日、カブオ君はスマホばかり見ていたわね。含み益が減っていくと騒いでいたわ。
認めます。先生、灯台のように行き先を示してください。
目次
トランプ関税で株価暴落 どうしよう! 配当重視の株も……
無理です。わたしの大好きな作家、村上春樹は『1Q84』で青豆が『歴史が人に示してくれる最も重要な命題は“当時、先のことは誰にもわかりませんでした”ということかもしれない』と語っていますが、そのとおり。明日どころか1秒先もわからないのが現実です。
先生の語りも村上春樹風になっていますね。
村上春樹はわたしより約11歳年上で、生きてきた時代も違いますが、神戸や夙川、芦屋といった同じ地域に育ち、同じ高校に通い、大学は違いますが、上京した私にとって『ああ、その感じ』と思うことが多いんです。語りだすと長くなるので、このへんでやめましょう。
話は戻りますが、配当を重視する投資スタイルの人はそれほど動揺していないのではないでしょうか。
配当重視で買った株でも強烈に値下がりしていますよ。
例えば3,000万円で投資用マンションを買って保有しているとします。利回り4%、年間120万円、月10万円の家賃収入を得ているとしますね。
そういう生活がしたい……。
一方、同じ3,000万円で利回り4%の株式やREIT(不動産投資信託)でも保有しているとします。税制上の違いは別にして、こちらも年間120万円、月平均10万円の配当金収入を得ているとします。
株式の場合、常に時価が明らかで、暴落局面では悲嘆にくれるわけですね。しかし不動産だったらどうでしょう。不動産にも価格があって実質的に下がっているかもしれませんが、毎日わかるものではなく、一喜一憂のしようがないですね。それより入居率や銀行借入金利がどうか、毎日の清掃状況など、オーナーはそんなことを考えるわけです。
株式も投資した後は株価よりも企業の状況に関心を持てばいいし、そのために四半期ごとの数字はリアルで役に立つと思いますよ。
なるほど、少し気持ちが落ち着きました。
配当重視の人の心がざわざわしているとすれば、“買いたいのに軍資金がない”というロス感じゃないですか。こういうときはバラエティ番組でも見て笑っているほうが健全ですよ。
さて、配当ですが、表を見てください。最もわかりやすいのは配当利回りですね。
| 項目 | 単位 | 2020年3期実績 | 2021年3期実績 | 2022年3期実績 | 2023年3期実績 | 2024年3期実績 | 2025年3期計画 | 4/4 株価 | 4/7 株価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1株あたり年間配当金 | 円 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| 2 | 期末株価 | 円 | 2,545 | 3,055 | 3,330 | 3,425 | 3,740 | 4,150 | 3,930 | 3,650 |
| 3 | 期末株配当利回り | % | 2.75% | 2.62% | 2.70% | 2.92% | 2.67% | 2.65% | 2.80% | 3.01% |
| 4 | 1株あたり当期純利益 | 円 | 188.53 | 356.95 | 430.83 | 539.1 | 548.61 | 589.35 | 589.35 | 589.35 |
| 5 | 期末PER | 倍 | 13.5 | 8.6 | 7.7 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.2 |
| 6 | 配当性向 | % | 37.1% | 22.4% | 20.9% | 18.5% | 18.2% | 18.7% | 18.7% | 18.7% |
銀行の預金金利が上がっているのに、正直2%台はあまり魅力がないわ。ネット銀行なら1%あるし、元本も減らない。
参考までに、急落した4月4日と7日の株価での利回りを示しておきました。4月7日だと3%に届いていましたね。
しまった! 買っていない
最近は年に一度は急落局面がありますから、海の底で獲物が落ちてくるのをじっと待つ魚のように構える作戦もいいですね。
前回までの講義でお話ししたように、極洋は中期計画でDOE(株主資本配当率)を3%以上にすると定めています。1株あたり純資産が5,000円なら、150円の配当金を示しています。株価4,000円なら3.75%、4%を狙うなら3,750円で買いたいですね。
利益が減って配当性向は上昇…… 喜べますか?
次に配当性向を見てください。計算式は、
配当性向(%)=1株あたり配当額÷1株あたり当期純利益×100
でしたね。20%を切る水準をどう思いますか?
ふつうは30%~50%くらいだと思うので、低すぎると思います。
同業他社を調べてみてください。
2024年3月期ですが、
・1333 マルハニチロ…… 20.6%
・2875 東洋水産…… 29.4%
・1332 ニッスイ…… 31.3%
あれ、それほど高くないな?
企業側からすれば、配当するということは資金が外部流出するということです。企業経営には運転資金や投資資金、財務資金などが必要ですし、特に成長過程にある企業は配当よりも投資に回したいという考えが当然あります。無配の会社もありますが、株主がそれをどう受けとめるかは別です。
会社によって事業構造は異なりますが、この業界の平均は20%~30%程度かもしれません。マナミさんが言うように、せめて25%、ぜひ30%はほしいですね。ただし、利益はかなり変動しやすいものなので、注意が必要です。
と言うと? 配当性向が高ければ高いほど株主のほうを向いていると思うのですが?
配当が変わらず、利益が減れば配当性向は上昇します。喜べますか?
うーん。配当は減らなくても、利益が減ると株価も下がる?
そうすると配当利回りは上昇します。喜べますか?
うーん…… 悩みますが、喜べません。
そうですね。配当利回りや配当性向は重要な指標ですが、それだけで投資を判断するのは危険なのです。わたしが警戒するのは増配銘柄です
増配銘柄というと、好感されるのでは?
そのとおりです。利益や純資産が増え、将来への投資資金も確保したうえでの増配ならよいでしょう。しかし、株価対策や株主重視のためだけに増配するのは感心しません。連続増配銘柄リストというのもあって、“さすが”という会社が並んでいますが、あえてじっくり検討したいですね。経営者にとって連続増配というのは賞賛される一方、常に大きなプレッシャーを受けているのではないかと思ってしまいます。
では次回は、まとめの⑤として、経常利益の増減とPERなどについて学びます。ここまでくればかなりの知見が身についていると思います。こんな相場だからこそ、知識を力に変えて頑張りましょう。
はいっ!
プロフィール

井上 享(いのうえ・すすむ)
日本公認不正検査士協会認定 公認不正検査士(CFE)1982年に慶應義塾大学法学部政治学科を卒業後、大阪銀行(現:関西みらい銀行)に入行。退行後、会計知識、法律知識、犯罪心理学、調査手法の4つの分野の試験に合格し、かつ米国公認不正検査士協会の認定よって与えられる公認不正検査士(CFE)の資格を取得。金融関係の不正行為・不祥事を防ぐべく、活動している。
主な著書に「銀行不祥事の落とし穴 第1巻、第2巻」、「中小企業融資自己査定Q&A」、「説明義務・勧誘ルールと苦情対応事例集」(いずれも、銀行研修社)。現在、月刊銀行実務(銀行研修社刊)に「金融不祥事 転落の死角」、金融経済新聞に「STOP! 不祥事!」を連載中。 ドラマ「幸せになる3つの買い物」監修、映画「シャイロックの子供たち」銀行監修。 兵庫県神戸市出身。