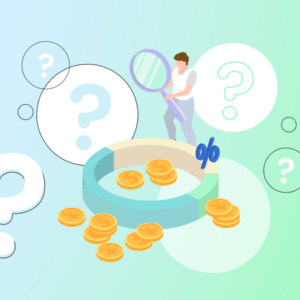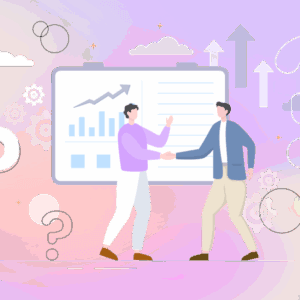【塚本俊太郎の金育 第10回】“じぶん年金”の受け取り時にかかる税金は?
金育コラムの最終回は、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DC(企業型確定拠出年金)などの“じぶん年金”の受け取り時の税金について、詳しく見ていきます。
iDeCoや企業型DCは、掛金を払い込む時に税金が一部戻ってくる代わりに、年金を受け取る時に税金を払うという制度になっています。掛金を入れてから受け取るまで税金を繰り延べる、つまり税金の支払いを先延ばしにするという考え方です。
受け取り方法には、1回で全部受け取る「一時金」と、毎月または2か月に1回といったように定期的に受け取っていく「年金」の二つの方法があります。どちらか一つだけ選ぶこともできますし、一部は一時金にして、残りを年金で受け取る“併用”を選ぶこともできます。
目次
iDeCoや企業型DCの受け取りは「一時金」と「年金」がある
日本の年金制度の中で、iDeCoや企業型DCはいわゆる“3階建て”の部分(私的年金)に当たります。文字どおり、“じぶん年金”というわけです。
そんなiDeCoと企業型DCですが、税金面では一時金で受け取る場合、退職所得控除が使えます。勤続年数が20年までは毎年40万円の控除が受けられ、20年を超える部分は毎年70万円の控除が受けられます。
一時金で受け取る金額からこの控除金額が差し引かれて、残った部分の金額の2分の1(半分)に税金がかかるという仕組みです。
例えば30年間働いた人が2000万円の年金積み立てがある場合、最初の20年は20年✕40万円=800万円、残りの10年は10年✕70万円=700万円、合わせて1500万円までこの退職所得控除が使えます。2000万円―1500万円=500万円、その半分の250万円に税金がかかる計算になります。
受け取り金額が1500万円未満だったら税金はかからないということになりますね。現時点の税金面でいうと、この一時金で退職所得控除を使うのが基本的には一番有利だといわれています。
では、年金受け取りのケースを見ていきましょう。毎月または2か月に1回決まった金額を受け取るときは公的年金等控除が使えます。65歳未満の人は年間で60万円までこの控除が使えて、65歳以上になると年間で110万円までこの控除が使えます。この年金受け取り以外にも、国民年金や厚生年金などの収入がある場合はその収入と合算して、控除額を差し引いた残りの部分に税金がかかることになります。
そんなに年金額が多くない場合や、他の収入も多くない場合はこの公的年金等控除が使いやすいでしょう。ただ、一時金受け取りを選んだ場合の退職所得控除額が大きいため、一時金受け取りを選ぶ人が多いようです。
退職所得控除についての内容は、私のYouTube動画「iDeCo 難しい出口戦略」(iDeCoの受け取り方とその際の税金がお得になる方法について説明しました /youtube.com)で説明しているので、こちらをご覧いただきたいと思います。
お金の学びは一回でおしまいではありません!
さて今後、税金がどうなっていきそうか――。今後の税制変更の可能性について、少し触れておきたいと思います。
iDeCoや企業型DCは、元来、人々の老後の資金として活用してほしいという目的なので、本来は年金受け取りを選んでもらったほうがいいと思います。しかし、いまの税制では一時金で受け取るほうが税制面で有利となっています。おそらく、今後は年金として受け取ったほうが税制上も有利になるように、制度が変わっていくのではないかと思っています。
今年こうした年金制度の見直しが入っているので、議論が進んでいくのではないでしょうか。
また、iDeCoや企業型DCの掛け金を増やすことも検討されています。これから非課税で運用できる“じぶん年金”を増やすチャンスが拡大されていく可能性が大きいと思われます。
さて、最後になりますが、2022年から高校での金融教育が拡充され、いま金融教育が話題になっています。時代の流れといえそうですが、最近では「高校で学ぶのはいいけれど、大人になると学校で勉強する機会がなくなるので、どうしたらいいんでしょうか」という声をよく耳にしますが、お金とどうやって付き合っていくべきか、どのようにさまざまな制度や金融商品を活用するべきなのかは、みなさん一人ひとりが、一生かけていろいろなタイミングで勉強していく必要があると思っています。
例えば、家を買う時には住宅ローンの仕組みや借り方を学ぶことができます。クレジットカードを日々の生活の中で使うことが多いと思いますが、どういう利点があって、どういう注意点があるのかを自分で調べてみることは大事です。最近ではQRコード決済が増えていますが、他の決済方法と比べて、どういうメリットとデメリットがあるのかを調べたりするのもいいでしょう。いろいろな時点で必要に応じて金融商品やサービスについて調べ、自分に合った活用をして、自分の生活を豊かにしていくということが大事な考え方だと思います。
お金について、一回学んだらおしまいではなく、一生かけて、その時その時に必要なものを学んでいくというスタンスで臨んでもらえるといいですよね。かくいう私も、時代とともに変化する金融について日々学んでいますので、みなさんも一緒に金融の学びを続けていきましょう。
(塚本俊太郎)
プロフィール
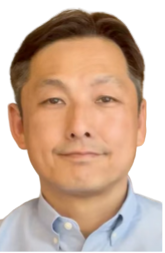
金融教育家 塚本俊太郎ホームページ
1994年、慶應義塾大学総合政策学部を卒業。97年に米国シラキュース大学大学院国際関係論を卒業。20年以上、外資系運用会社で勤務したのち、金融庁の金融教育担当として高校家庭科の金融経済教育指導教材や小学生向け「うんこお金ドリル」の作成を担当。現在は金融教育家として、金融リテラシーや資産形成について講演活動などを行っている。
2023年3月期 Eテレ「趣味どきっ! 今日から楽しむ“金育”」講師。
YouTube「塚本俊太郎の金融リテラシーチャンネル」
日本金融教育推進協会理事。グリーンモンスター株式会社顧問。日本CFA協会執行理事。NewsPicks ProPicker。