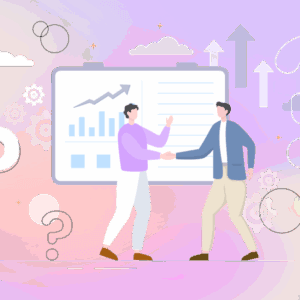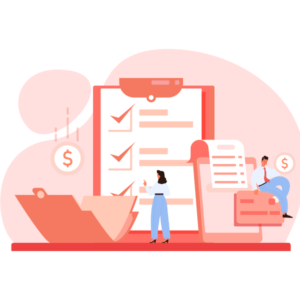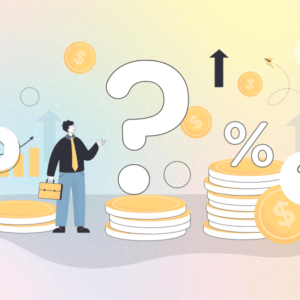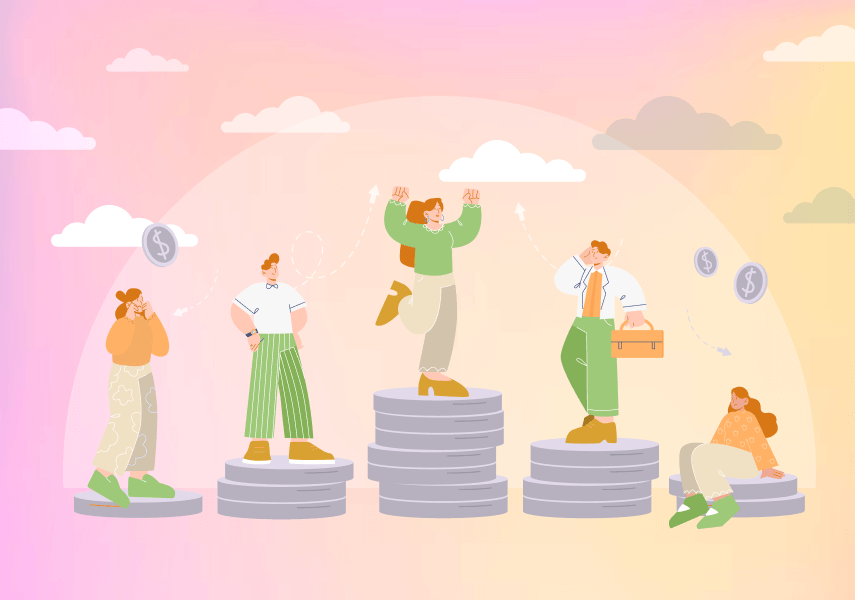
外国為替と企業収益の関係 為替の基本の「キ」を学ぼう③
外国為替レートは、国と国とのあいだで商品やサービスを交換する際の通貨の交換比率を示します。この為替レートの変動は、輸出入を行う企業の収益に直接的な影響を及ぼします。特に日本のような輸出入が盛んな国では、為替レートの変動は企業経営にとって、とても重要な要素となります。
今回は、外国為替が企業の収益に与える影響と具体例をご紹介します。
目次
為替レートと輸出入企業の影響
輸出企業
円安は輸出企業にとって有利です。円安になると、外貨での収益を円に換算した時、より多くの円が得られるためです。これにより、海外での販売価格を下げて競争力を高めるか、あるいは販売価格を変えずに利益を増やすことが可能になります。
それでは、貿易を行う企業が為替レートの変動でどの程度収益が変動するのか、輸出企業の具体例をご紹介します。
具体例:トヨタ自動車
トヨタ自動車は、世界最大級の自動車メーカーの一つであり、その収益の大部分は海外市場から得られています。円安が進むと、トヨタは海外で売ったクルマの収益を円に換算した際に、より多くの収益を得ることができます。例えば、ドルで1000万ドルの収益があった場合、1ドル=100円の時は10億円の収益ですが、1ドル=110円の円安時には11億円の収益になります。日本経済新聞の記事によると、2023年時点において、トヨタは1円の円安で450億円の営業利益が増加するとされています。特に、自動車メーカーや重工業メーカーは、円安になると企業収益が拡大するといわれています。
輸入企業
円高は、輸入企業にとって有利です。円高になると、同じ金額の円でより多くの外貨を手に入れることができるため、結果として輸入コストが下がります。これにより、商品の仕入れ価格を下げることができ、利益を増やすことが可能になります。
それでは、貿易を行う企業が為替レートの変動でどの程度収益が変動するのか、輸入企業の具体例をご紹介します。
具体例:ニトリホールディングス
日本の小売業の一部は、海外から製品を輸入するか、海外の工場で製造した商品を輸入しています。円高になると、これらの企業は外貨での支払いが円で少なくなるため、仕入れコストを削減できます。例えば、1ドル=110円から1ドル=100円に円高が進めば、同じ1000万ドルの製品を輸入する際のコストは、11億円から10億円に減少します。この削減分は利益増加につながるか、または消費者に価格削減として還元することが可能です。家具販売大手のニトリホールディングスは、多くの商品を海外で製造。国内で販売しています。そのため、為替が1円の円高になることで、20億円の営業利益が増加するとされています。
日本は、医薬品や一部の食料品を輸入に頼っています。また、iPhoneなどの電子機器や、ネットフリックスなどのオンラインサービスも、為替相場の影響を受けるため、円高のメリットがあるといえます。
企業は、業績の見通しや事業計画を決める際に、事前に決めておく「想定為替レート」を発表しています。そのレートから為替相場が変動することで、企業が予測している利益が変動する主な要因とされています。
為替レートの変動は予測が難しい……
為替リスクの管理
為替レートの変動は予測が難しいものの、前述のように企業の収益に大きな影響を与えます。そのため、多くの企業は為替リスクの管理に注力しています。
その方法として、先物取引やオプション取引を活用して未来の為替レートをある程度固定するヘッジ取引があります。また、為替相場の変動に応じて海外の生産拠点を増やすことで、為替変動の影響を受けにくい体制を整える企業もあります。
デリバティブ取引の損失例
ヘッジ取引を行うことで、利益を守り、大きな損失を防ぐ対策となります。しかし、想定外の相場変動が起きると、大損を被ってしまうケースもあります。
例えば、日本航空(JAL)は1985年8月から86年3月にかけて、最長11年物長期為替予約を行いました。当時のドル円相場は250円前後で推移していました。ここから上昇すれば、この予約は成功。下落すれば失敗という契約です。
その後の11年で、ドル円相場は200円を割り込むばかりか、100円を割り込み史上最安値を付けるほどの値動きが発生しました。この契約によって同社は2200億円の損失が発生したとされています。
このように、為替レートの変動は、企業の収益に直接的な影響を及ぼすため、適切なリスク管理が不可欠だとわかります。
為替のおさらいクイズ

プロフィール

児山 将(こやま・しょう)
2009年からFXトレードを開始。強制ロスカットを10数回ほど遭遇しながら、2013年に収益が安定。金融メディアで、FXのWEBサイトの運営や記事制作、個人投資家への取材などを担当。ファンダメンタルズ分析の知見を養う。
2018年に投資家兼フリーランスとして独立。日本株、米国株、仮想通貨、商品など多数の金融商品を取引。YouTubeでは、ファンダメンタルズ分析と需給、イベント、統計データなどを発信中。