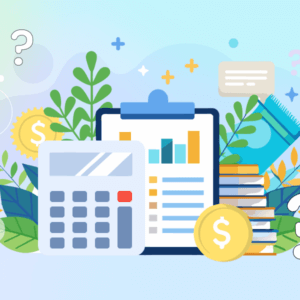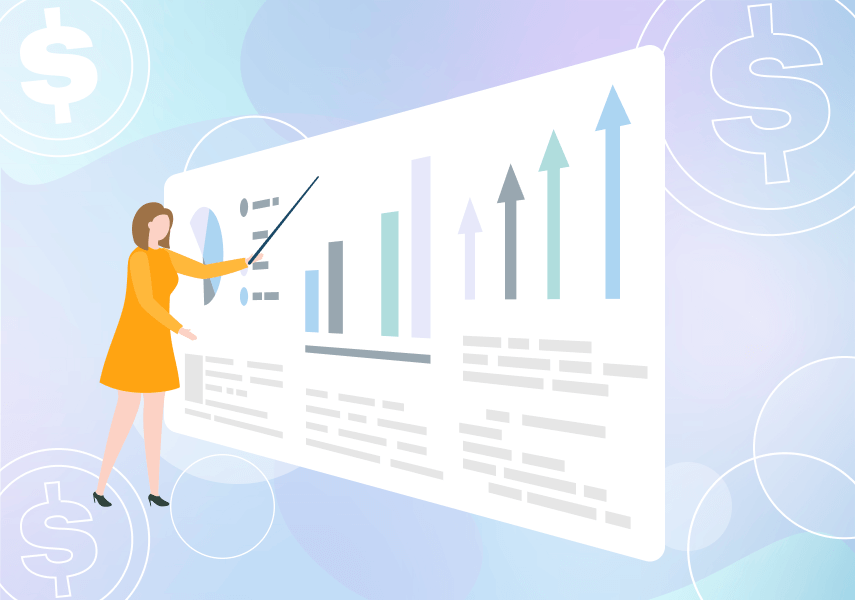
【第22話】「NISAはやるべきか 始めるならどうすればいい?」 ススム先生の「タイパ決算書分析」塾
「タイパ決算書分析」塾、第23回です。今回は番外編として、「NISAはやるべき? 始めるならどうすればいいのか」考えたいと思います。
考えるもなにも、当然やるべきです!
目次
NISAのメリットは「利益」に課税されないこと
じつは先日、親戚の集まりがあったのですが、姪から「NISA、NISAってよく聞くけど、やっておいたほうがいいのかな? さっぱりわからない」と質問を受けたんです。
姪の属性を説明しないと具体的な話ができないので補足すると、姪は私の妻の姉の娘で、人口約12万人の地方都市に住んでいます。30代後半、本人は看護師、夫は地方公務員、子供3人、自宅所有、という一家です。
恵まれている感じですね。羨ましい。
素敵なスポーツ一家ですよ。これ以上の詳細は私もわかりませんが、属性からすれば世帯収入はそこそこありますし、住んでいる地域の地価から想像すると住宅コストはそれほど高くないと思います。
確かに人口減少が見られる地域ですが、基盤となる産業がしっかりしていて投資マネーも入っているようなので、衰退していく感じはない地域ですね。
都会で住宅なんて買えないし、カノジョにも巡り会わないなあ。
カノジョはカブオ君の個人的な問題だよ。
順番に整理しましょう。なぜNISAを利用すべきと主張するのですか?
譲渡益や配当金、分配金などの利益に課税されないことが最大のメリットです。通常だと所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%、合計20.315%の税金がかかります。NISAを利用しない理由はないと思います。
そうですね。損益通算や繰越控除ができないというデメリットもありますが、カブオ君の言っていることに誤りはないですね。
税制に加えて、投資経験がない人たちのきっかけになることも大切なポイントだと思っています。大損をする、魑魅魍魎が跋扈する世界、そういったイメージが多少なりとも改善する契機になるといいですね。もちろん全資産を投資に振り向けるのは論外ですが、インフレへの備え、という意味でも投資を避けてはいけないと思います。預貯金に集中し過ぎて資金が目減りする事態は少しでも避けたいですよね。それと若い時期からスタートするのはとても意味があります。有価証券投資の醍醐味は複利で増えていくことですから、時間があればあるほど有利に膨らんでいきます。時間を味方につけることが肝心です。
ちなみに1年で倍にした、といった話は疑わしい武勇伝がほとんどですから近づかないように!
ところでマナミさん、NISAの限度額は?
株などが買える成長投資枠が年間240万円、毎月積立のためのつみたて投資枠が年間120万円です。生涯限度額は1800万円、そのうち成長投資枠の限度額が1200万円で、残りがつみたて投資枠となります。期間の制限がなく非課税で保有できるので安心です。
では、どういう考え方でNISAを利用すべきですか?
短期の利益を求めず、安全に、長期投資で…… かな?
それも一つの解ですが、私が最も大切だと思うのは、「無理なく長続きできる金額で!」ということです。NISAの投資対象は預貯金と違って元本が変動する商品です。お子さんが3人いて将来教育費もかかるでしょう。一番の失敗は、資金が必要になって仕方なく換金する、という行為です。長い目で見れば右肩上がりでしょうが、将来のことなんてわからない。戦争、政変、天変地異、海外の動乱、世界的な景気悪化など、なんでも起こりうる世の中です。相場が悪いタイミングに当たると目も当てられません。
欲に耐え、むやみに情報を見ない、安易な儲け話を聞かない
難しくなってきました。先生、要点をまとめてください。
では、箇条書きにしましょう。
① NISA口座を作る
オススメはネット証券です。銀行でも大丈夫ですが、姪の地域の地方銀行や信用金庫はあまり前向きではないようです。証券に抵抗があるならメガバンクのネット口座でもいいです。銀行の窓口で相談するのはオススメできません。銀行員はセールスのプロですが、運用のプロではないことは肝に銘じておきましょう。複雑なことをする必要はないので、自分に主導権があるネット証券のほうが実は安全です。
② まずはつみたて投資枠
「投資」というと儲け、損、と考えがちですが、まずはつみたて投資枠を活用しましょう。高い時に集中して買ってしまうリスクを避けるため、毎月一定額を買っていく、時間分散する退屈な投資です。ドルコスト平均法などと呼ばれます。集中投資に比べて安全、といった記事も散見されますが、必ずしもそうとは限りません。要は現金化する際の相場が問題なのですが、将来のことは誰にも分からない。ただ毎月投資をしていくので、錯覚もありますが、増えていく実感は得やすいでしょう。
③ いくら投資するか
その家の家計によりますが、あまり少額だと退屈します。毎月5万円が下限でしょうか?
夫婦でそれぞれ口座が作れます。一人暮らしであれば、1~2万円が下限でしょう……。
④ 何に投資するか
つみたて投資枠では個別株式は買えなくて、限られた投資信託とごく一部のETF(上場投資信託)に限られています。要するにリストにある投資信託から選ぶだけです。日経平均株価やS&P500、全世界株式など特定の指数に連動するインデックス型が、コストが安くわかりやすいので初心者にはいいでしょう。上がっても下がっても余分なことは考えず、淡々と積み立てるのです。
⑤ 失敗しないために
つみたて投資枠に慣れたら余裕資金で成長投資枠に挑戦するのも悪くないです。ただ、資金を一銘柄に集中しないことです。倒産しても精神的なショックが少ない金額(例えば30万円や50万円など)に抑えて経験していくことです。投資は義務ではありませんから無理しないことです。
加えて大事なことは、投資を始めたらいろんな情報が飛び込んできますし、ついつい目が向きがちです。しかし、これらは玉石混淆で、投資詐欺も少なくありません。これらを見極めるのは極めて困難です。従って、欲に耐え、むやみに情報を見ない、安易な儲け話を聞かないことが損をしない最大のポイントです。
私は個別株が大好きなのですが、確かに、つみたて投資枠でベースを固めると精神が安定する気がします。
ボクは半年くらい前から先進国株式と新興国株式を毎月同額積み立てています。含み益は今のところ、イメージと相違して新興国のほうが大きいです。
時には初心に帰って頭をリフレッシュしましょう。
はいっ!
プロフィール
 井上 享(いのうえ・すすむ)
井上 享(いのうえ・すすむ)