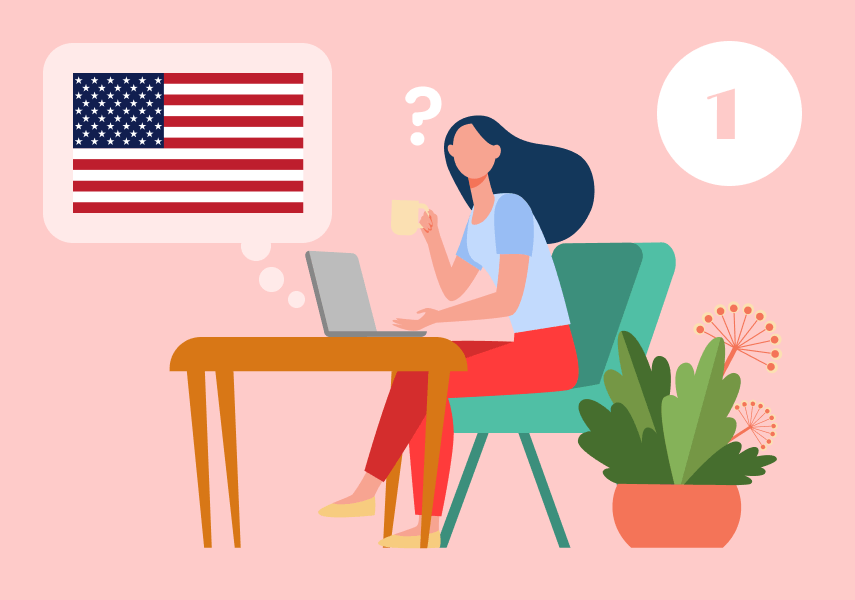
【第1回】米国株は有望だ! いきなり米国株投資って大丈夫?
株式投資をやったこともないのに、いきなり米国株の投資って無理なのでは……。そう思う人も多いでしょう。
でも、大丈夫!
米国株の取引時間は、米国の標準時間なら日本時間の午後11時30分から翌日午前6時、夏時間の時期には午後10時30分から翌日午前5時です。だから日中は忙しく、市場の動きを見ることができない人でも、米国市場の動きはリアルタイムで見ることができるのです。
ただし、大切なお金を投資するのですから、やっぱり、少しは知識を持って投資を始めたほうがいいですよね。そこで、米国株投資について、株式投資が未経験の人でもわかるようにお話ししていきましょう。
目次
なぜ、米国株への投資は有望なのか
米国株は日本株よりも「将来性が高く、有望」「オトク」「投資しやすい」……。そんなことを聞いたことはありませんか? ここ数年、そう思って米国株投資を始める個人投資家は少なくありません。
では、まずは「米国株への投資が、なぜ有望なのか」から、お話ししましょう。
急成長企業がいっぱい
米国は言わずと知れた世界一の経済大国です。
OECD(経済協力開発機構)の2022年のGDP(国内総生産)成長率は、日本が1.1%だったのに対して、米国は2.1%の成長を遂げています。
経済の低成長が続く日本とは違って、米国は高い経済成長を続けています。
日本は少子化の影響で、人口減少が続いています。米国も少子化傾向にあるのは日本と同じですが、毎年、多くの移民がある米国では、移民によって人口増加が続いています。
人口が多いというのは、新たな労働者人口が生まれ、それに伴った消費が生まれるため、経済が成長するための大きな要素です。
こうした経済の安定を背景に、米国では多くの企業が成長を続け、グローバルに展開している大企業がたくさんあるのです。
また、米国は政治的にも安定した国ということができるでしょう。
政治の安定、国の経済成長、企業の成長力は、株価が上昇するための重要な要素なので、これらの要素が備わった米国企業への株式投資は、魅力ある投資だと言えます。
米国企業には、急成長企業がいっぱいあります。
例えば、世界的なIT企業であるGAFAM(グーグル、アマゾン、フェイスブック〈現メタ・プラットフォームズ〉、アップル、マイクロソフト)などはすべて米国企業です。
企業の価値を計る代表的な指標のひとつに「時価総額」というのがあります。時価総額は株価×発行済株式数で計算できます。時価総額が大きいということは、その企業の価値が高いというになります。企業価値が高ければ、経営は安定し、企業は必要な資金調達がしやすくなり、新たな投資などを行いやすくなります。
世界の大企業の時価総額ランキングでは、トップ10のほとんどを米国企業が占めています。2022年末の世界1位の時価総額はアップルの約2.07兆ドルでした。1ドル=140円で計算すると、約290兆円になります。トヨタの時価総額が約30兆円でしたので、アップルの時価総額は、トヨタの約9.7倍にもなります。
積極的な株主還元
米国株が上昇する大きな理由の一つとして、株主還元に積極的なことがあげられます。
日本の企業は年に1~2回(中間・期末)の配当が一般的ですが、米国企業の多くは四半期ごと(年4回)に配当を行っています。そのうえ、利回りが年5%を超えるという高配当企業も多く、さらには連続して増配を続けている企業も多いのです。
米国の代表的な株式指数「S&P500指数」を構成する株式銘柄のうち、過去25年間連続して毎年増配している企業だけを選んで、「配当貴族指数」という優良大型株指数まであります。
その中には、50年、60年という長期間にわたって増配を継続している企業があるのですから驚きです。
また、米国企業は自社株買いにも積極的です。自社株買いとは、企業が自分の会社の株を購入するもので、多くは市場の取引価格よりも高い値段で買い入れることや、自社株買いによって、市場で流通する株式数が減少することで、株価上昇の大きな要因になります。
日本企業の自社株買いは年間で総計6兆円程度ですが、米国企業では年間で総計80兆円程度が行われており、日本企業の10倍以上の自社株買いが実施されているのです。
なぜ、米国株への投資が有望なのか、について述べてきましたが、このように米国株への投資は日本株への投資にはない魅力がたくさんあるのです。
プロフィール
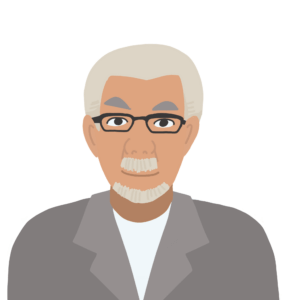
鈴木 透(すずき・とおる)
経済ジャーナリスト / カブライブ! 編集長
ロイター通信編集委員。外国為替、債券、短期金融、株式の各市場を担当後、財務省、経済産業省、国土交通省、金融庁、検察庁、日本銀行、東京証券取引所などを担当。「鷲尾香一」の執筆名で、マクロ経済政策から企業ニュース、政治問題から社会問題まで、さまざまな分野で取材、執筆活動を続けている。
2023年9月から、カブライブ!編集長








