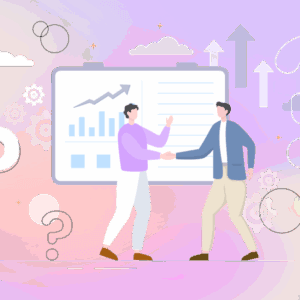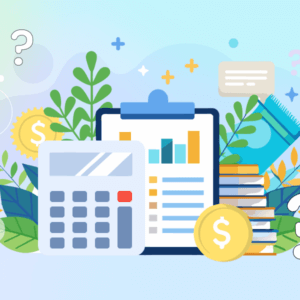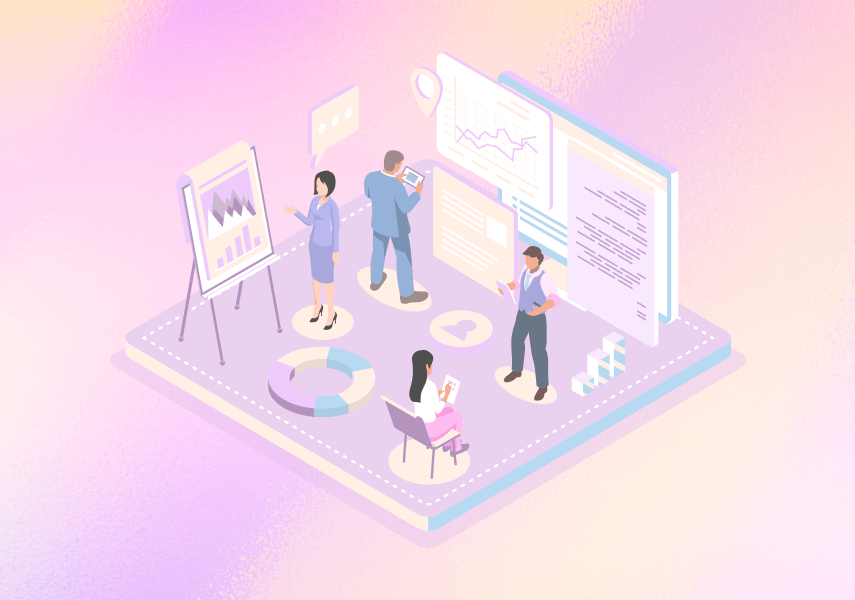
【第19話】そろそろタイパを身につけたい! まとめ③ ススム先生の「タイパ決算書分析」塾
「タイパ決算書分析」塾、第19回。今回はタイパな分析のまとめ、3回目です。
決算書やIR資料も見慣れてきましたし、時間はかかりますけれども基本的な分析についても理解できました。そろそろ、タイパを身に着けたいです。
そうですね。では、今回も「極洋」で見てみましょう。さっそく、主要項目をピックアップしましょう。
おおっ! そのお言葉を待っていました。
ただし、これは私のやり方であって正解というわけではありません。100人いれば100とおりの投資があっていいし、それによって相場が形成されるのですから。私はどんどん株価が上昇する成長企業を見つける能力はないので、一般的にいえば、バリュー型(企業の収益力や資産状況等の情報から、株価を評価する手法)に含まれると思っています。
銀行員の多くは倒産したり返済が遅延したり業績が悪化したりした企業と取引してしまうことは最大の屈辱なので、どうしても保守的な見方に支配されがちなのかもしれません。
なんとなくわかります。
目次
自己資本比率と自己資本に注目!
では、まず自己資本比率と自己資本に注目しましょう。
純資産の実額がしっかりしていて、自己資本比率も一定数以上をキープしているかどうか注目しましょう。以前に学習したように、自己資本比率が低く、かつ利益率が高い企業に投資することも株式投資の醍醐味ですが、利益成長の見極めが難しい。少なくとも債務超過に近いような、数期赤字が続いたら債務超過になるような企業は避けましょう。日本の上場会社は約4000社もあるので、あえてそのような“キワモノ”を選ぶ必要はありません。
| 項目 | 単位 | 2020年3期実績 | 2021年3期実績 | 2022年3期実績 | 2023年3期実績 | 2024年3期実績 | 2025年3期計画 | 2026年3期計画 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 純資産 | 百万円 | 32,593 | 39,975 | 42,174 | 46,966 | 58,860 | ||
| 2 | 自己資本比率 | % | 29.4% | 34.7% | 32.7% | 32.5% | 36.7% | ||
適切な自己資本比率の水準とは、どのくらいでしょうか?
高ければ高いほど安全性は高まり、50%がメドという人もいますが、明確な定義はありません。業種の特性を知りましょう。銀行などの金融業とメーカーでは違います。推移をチェックしましょう。極洋のように30%台でも何年も安定し成長している企業があります。金融機関などの理解を得ながら、30%台でより高い利益を生み出しているといえるでしょう。
「率」そのものに加えて、業種特性、会社の業績の推移をチェックということですね。
そのとおりです。次の注目点は1株あたり純資産、株価純資産倍率(PBR)と株主資本配当率(DOE)です。マナミさん、どうですか?
| 項目 | 単位 | 2020年3期実績 | 2021年3期実績 | 2022年3期実績 | 2023年3期実績 | 2024年3期実績 | 2025年3期計画 | 2026年3期計画 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1株あたり純資産 | 円 | 3,046.26 | 3,753.90 | 3,969.73 | 4,436.27 | 4,965.39 | ||
| 2 | 期末株価 | 円 | 2,545 | 3,055 | 3,330 | 3,425 | 3,740 | ||
| 3 | 期末PBR | 倍 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | ||
| 4 | 1株あたり年間配当金 | 円 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | |
| 5 | 株主資本配当率 | % | 2.3% | 2.1% | 2.3% | 2.3% | 2.0% | ||
1株あたり純資産も順調に増加し、株価も上昇しています。配当も増配傾向ですので、安定的に成長していると思います。PBRとDOEはどのように評価していいのかわかりません。
そうですね。1株当たり純資産はまさしく株主の持ち分なので、増加を確認してください。一過性の赤字もありますが、これが慢性的に減っているような会社には近づかないことです。株価の形成は複雑ですが、極洋はコロナ禍の時期も含めて右肩上がりなので市場の評価や反応は悪くないことを実感すればいいと思います。配当金は会社の株主還元の姿勢も反映します。株主は増配を歓迎しますが、会社にとっては資金流出の要因でもあるので経営判断は簡単ではありません。
PBRとDOE、どう捉えればいい??
計算式は知っていますが、ぼくもPBRやDOEの捉え方がわかりません。
PBRは株価純資産倍率を指し、計算式は
株価÷1株当たり純資産
です。例えは今、極洋が解散した場合のことを考えてください。1株あたり純資産は1株あたりもらえる金額で、極洋の場合は4,965円です。一方、期末株価は3,740円なので、0.75、つまり市場は0.75倍の評価をしているということです。
差額の1,225円の意味は……?
株価が1株当たり純資産に完全に連動していれば同額、1倍になりますが、株価は純資産面だけを評価しているわけではないので、差額が発生します。解散価値だけでいえば、実際、会社が解散する場合は資産を現金化し、この過程で含み益や含み損が実現し、負債を清算し、従業員には退職金を支払い、課税分を支払い、これらの費用を払った後の残高を分配することになります。結果、1株あたり純資産の金額とは差が出ます。ただ、これを緻密に計算することは不可能です。
では、PBRの使い方は?
まず低すぎないか、をチェックすることです。低すぎる銘柄はオトクだと思うかもしれませんが、市場はそんな銘柄を放置しません。したがって、放置されている銘柄には理由があるはずです。「低PBRの罠」という言葉があるくらいですから。
次に高すぎないか、です。人気株は純資産価値を相当にオーバーしているケースがあります。将来の利益を先取りしているともいえますが、割安ゾーンの可能性は高くないでしょう。
2023年3月、東証は「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」の要請を実施し、昨年1月には対応策を開示している一覧表の公表を開始しました。経営者はさまざまな経営課題の一つとして株価を意識することをしてください、その一つの目安がPBRということすね。
極洋のケースでは、2024年3月末は0.75倍です。「不合格ではないですが、優等生というわけでもない」といったゾーンです。高すぎるわけではないので、株価が大幅に下落する局面ではセーフティネットのような役割は果たすかもしれせん。
DOEはもっと難しそうです。
DOEは株主資本配当率を指し、計算式は
年間の配当総額÷株主資本×100(%)
で計算できます。1株当たりの数字で計算しても問題ないですね。株主に対する配当の積極性はどうなのか、という指標です。
配当って利益が基準なのでは?
もちろん、それは大切です。以前、配当金は利益処分案として決議されていたわけですから。ただ、利益はどうしても変動が大きいし、その都度、配当を上下させることは株主に対してどうなのか、という疑問があったことも事実です。DOEを意識するなら、株主資本はそれほどブレないので配当が安定するというメリットがあります。ただ、成長企業で利益が急拡大しているような場合は、配当が増えないという面もありますね。
配当は奥深いので、次回、配当利回りや配当性向と併せて学びましょう。
はいっ!
プロフィール

井上 享(いのうえ・すすむ)
日本公認不正検査士協会認定 公認不正検査士(CFE)1982年に慶應義塾大学法学部政治学科を卒業後、大阪銀行(現:関西みらい銀行)に入行。退行後、会計知識、法律知識、犯罪心理学、調査手法の4つの分野の試験に合格し、かつ米国公認不正検査士協会の認定よって与えられる公認不正検査士(CFE)の資格を取得。金融関係の不正行為・不祥事を防ぐべく、活動している。
主な著書に「銀行不祥事の落とし穴 第1巻、第2巻」、「中小企業融資自己査定Q&A」、「説明義務・勧誘ルールと苦情対応事例集」(いずれも、銀行研修社)。現在、月刊銀行実務(銀行研修社刊)に「金融不祥事 転落の死角」、金融経済新聞に「STOP! 不祥事!」を連載中。 ドラマ「幸せになる3つの買い物」監修、映画「シャイロックの子供たち」銀行監修。 兵庫県神戸市出身。